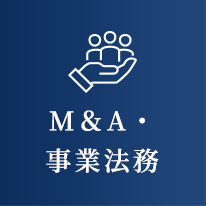株式譲渡対価の支払いに代えて役員退職金を支給する方法
株式譲渡益課税
会社の役員や従業員が会社の株式の譲渡を行った場合、譲渡益の20%相当のキャピタル税(株式譲渡益課税)が課せられることになります。従前は特例により上場会社の株式については10%の税率が適用になりましたが、現在では、上場会社の株式か非上場会社の株式かに拘わらず同じ税率(20%)が適用になることになっています。また、株式譲渡益については、申告分離課税とされていますので、他の所得(例えば事業所得や給与所得)とは損益通算はなされません。事業所得がマイナスの場合であっても、譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益に対する税金の支払いが必要となります。但し、同一年度に複数の株式譲渡がなされた場合は、株式譲渡相互間での損益通算がなされます。キャピタル譲渡益は売却価格から取得価格を控除して定められますので、取得価格がいくらであったかを明らかにする必要があります。なお、株主が法人である場合(別の会社が株主である場合)、譲渡益については、法人の所得となりますので、法人税に一本化されて課税されます。法人の所得がマイナスの場合、株式を一旦法人に移してから譲渡したほうが節税になる場合もあります。
贈与税
経営者が会社を退職する際に、後継者に株式を贈与することがあります。しかし、贈与を受けた後継者の側では贈与税の支払義務が生じてしまいますので、後継者に対して単なる贈与を行うのは好ましくありません。後継者が株式を適正対価で取得する場合は、後継者への課税はなされません。
会社による自己株式取得
会社に十分な配当可能利益がある場合は、経営者が所有する自己株式を会社が取得する方法も考えられます。会社による自己株式の取得については、配当可能利益が存在するほかにもいろいろな手続き上の制約がありますので、弁護士に確認ください。会社による株式取得についても取得価格が適正でない場合は、みなし配当課税がなされることもあります。
役員退職金の税金
役員退職金については、所得税と住民税が課税されます。退職所得については、実際に受け取った金額から退職所得控除額を差し引き、されに2分の1をかけた金額が退職所得となります。所得税の金額は、退職所得に、所得税の税率をかけて計算されることになります。
退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数が控除額となります。勤続年数が20年を超える場合、70万円×(勤続年数-20年)+800万円が控除額となります。すなわち、20年目までの控除額800万円と、20年目以降の控除額(年間70万円)を合わせた金額が控除額となります。
役員退職金課税と株式譲渡益課税の比較
例えば、役員としての勤続年数20年の役員が2000万円の退職金を受け取った場合、控除額は800万円となり、退職所得は、(2000万―800万)÷2=600万円となります。これに所得税と住民税の税率をかけたものが退職所得の税金ということになります。これに対してキャピタル税の場合、譲渡価格2000万円から取得価格を控除したものに対して20%の税金がかかることになります。どちらが有利であるかは計算してみなければ判明しませんが、多くの事例では退職所得のほうが税金は少なくてすむと思われます。そこで、中小企業のM&Aの場合、譲渡人である経営者の側からは、できるだけ退職所得を多くしてもらい、その分だけ株式の譲渡価格を少なくするよう要望されることがあります。但し、役員退職金は退職金規定があることが前提ですので、役員退職金規定が存在し、その退職金規定で定められた範囲内でしか退職金を支給することはできません。
功労加算倍率の制限
役員退職金の金額は、月額報酬×勤続年数×貢献倍率で定められることになります。役員退職金規定により貢献倍率は通常1から3に定められていると思いますが、貢献倍率が異常に高い場合には、税務署から否認されることがあります。過去の事例からすると、3.5倍が最大限でこれ以上の功労加算を行った場合は税務署から否認されるリスクが高くなります。どうしても役員退職金を多くしたい場合は、功労加算ではなく月額の報酬を大きくすることで調整するほうが好ましいです。但し、役員の報酬は毎月同額である必要があり、役員報酬の金額が月ごとに変動が生じる場合経費として認められない場合があります。
役員退職金の計算
功労加算を3とし、月額200万円の報酬を受領している経営者が30年勤務した後退職する場合の退職金の金額は、200万円×30年×3=1億8000万円となります。
生命保険を活用する場合の注意点
役員退職金の原資を準備するために生命保険に加入することが多いと思われます。生命保険の掛金が毎年費用となり節税効果があること、役員が死亡した場合は一時金の支給があり、役員の死亡によって会社に生じた損害を補填できることなどから生命保険の活用が多くなされています。しかし、生命保険については、生命保険の保険料を支払うことができずに途中で解約した場合の解約返戻金がどのくらいになるのか、生命保険の満期まで保険料を払い続けることができるのかをよく検討してから加入する必要があります。
企業法務の最新情報をお届けする無料メールマガジン