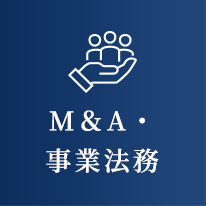事業譲渡の手続き・活用方法
事業譲渡とは
事業譲渡の概要
事業譲渡とは、端的にいえば、会社がその事業を他人に譲渡する取引行為です。事業譲渡は、株主の利益に重大な影響を与えるため、一部の例外を除き原則として株主総会の特別決議を経る必要があります(会社法467条1号2号、309条2項11号)。
会社法上、事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)、事業の重要な一部の譲渡(同項2号)、その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(同項2号の2)、他の会社の事業の全部の譲受け(同項3号)、事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約(同項4号)の行為が、「事業譲渡等」と定義されています(会社法468条1項)。
事業譲渡の意味は、判例(最大判昭和40年9月22日判決 民集19巻6号1600頁)が、次のような意味であると判示しました(※この判例は昭和40年当時の改正前商法の時代に出されたものであるため旧法の「営業の譲渡」の意味について判示したものですが、現行法の「事業の譲渡」の意味に関する判例として意義も持つと考えられています。)。
①一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(取引先関係等の経済的価値を有する事実関係を含む)の全部または重要な一部の譲渡であって、
②譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動を譲受人に受け継がせ、
③それによって譲渡会社が、法律上当然に、平成17年改正前商法25条(現行法でいうところの会社法21条)の競業避止義務を負担することになるものをいう、
とされました。もっとも、③については、競業避止義務は事業譲渡の結果として発生するものであり事業譲渡の要件には含まれないとする考えもあります。いずれにせよ、①②が事業譲渡の本質と捉えられています。
事業譲渡を事業譲渡を受ける側(買主側)から見ると、事業譲渡契約で定めた権利・義務(資産・負債)を承継することができるので、自身に都合の良い資産だけを承継する(いわゆるチェリーピッキング)が可能です。
事業譲渡の効果
事業譲渡といっても、一般的な取引行為と同様に、譲渡側の会社が有している権利・義務につき、権利は譲受人に譲渡し、義務は譲受人が引き受けることになります。事業譲渡は、一般的な取引行為を「事業」としてまとめて一括して譲渡を行っているにすぎません。そのため、民法の一般原則どおり、譲受人が義務(債務)を免責的に引き受ける場合は債権者の承諾が必要になりますし(民法472条3項)、権利の譲渡にあたっては権利の種類ごとに対抗要件を備える必要があります(ex民法177条、178条、467条)。
また、事業を譲渡した側の会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内においては、譲渡日から20年間は同一の事業が禁止されます(競業禁止義務(会社法21条1項))。譲渡会社が事業譲渡を行った後も自由に競業が可能としてしまうと、譲受会社のクライアントを奪う等の損失を譲受会社に与えかねないからです。とはいえ、当事者が別段の意思表示があれば、競業避止義務を軽減したり、あるいは排除したりすることも可能です。競業避止義務は譲受会社の自由な事業活動を大きく制限するものですから、実務的には特約で軽減または排除されるケースもあります。
なお、事業譲渡において、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する(商号の続用)場合には、事業譲渡契約で債務を引き受ける旨約定していなかったとしても、譲受会社は譲渡会社の債務を弁済する責任を負います(会社法22条1項。いわゆる“商号続用責任”)。商号続用責任の趣旨は、商号が続用される場合、一般消費者をはじめとする第三者は、譲受会社が譲渡会社と同一主体であると信じる可能性が高く、仮に同一主体でないことを知っていたとしても譲受会社は譲渡会社の事業を債務も含めてすべて引き継いだと信じることが通常と考えられるため、このような第三者の信用を保護することにあります。例外的に、事業譲渡後に遅滞なく、譲受会社が、譲渡会社の債務を弁済する責任を負わないとの登記をした場合(商業登記法31条)には、商号続用責任は発生しません(会社法22条2項前段)。また、事業譲渡後に遅滞なく、譲渡会社及び譲受会社が第三者である債権者に対して債務を弁済する責任を負わない旨を通知した場合の当該第三者に対しても同様に、商号続用責任は発生しません(会社法22条2項後段)。このように、意図せず譲渡会社の債務まで弁済する責任が発生してう可能性がありますから、商号を続用する場合には上記の登記や通知を行う必要があるか確認しましょう。
事業譲渡の手続き
株主総会の特別決議
事業譲渡を行うにあたっては、事業譲渡が効力は発生させる日までに、株主総会の特別決議を受ける必要があります(会社法467条1項、309条2項11号)。
なお、株主総会の特別決議での承認を得ないままに行った事業譲渡は、何人との関係でも当然に無効となります。つまり、相手方が事業譲渡につき譲渡会社にて株主総会の特別決議で承認を得ていないことを知っていようが知っていまいが無効となりますし、事業譲渡を受けた譲受会社も含めて誰でも事業譲渡の無効を主張できることになります(最高裁昭和61年9月11日判決 判時1215号125頁)。とはいえ、事業譲渡が実行されてから長期間が経過した後にはじめて当事者の一方が無効を主張することは、信義則に反するため当該無効の主張ができなくなる可能性があります(同判例)。
例外的に、①略式事業譲渡等(会社法468条1項)、②簡易の事業譲受け(同条2項)の場合は、株主総会の特別決議による承認が不要となります。①略式事業譲渡等とは、事業譲渡の相手方が、譲渡会社の特別支配会社(ある会社の総株主の10分の9以上を有する場合)である場合をいいます。10分の9以上の議決権を有している以上、株主総会で承認されることが明らかであるため株主総会での決議を省略しても問題ないという趣旨です。②簡易の事業譲受けとは、他の会社から事業の全部の譲渡を受ける場合に、譲受対価として交付する財産の帳簿価格が、当該譲受会社の純資産額の5分の1を超えない場合をいいます。譲受会社にとって事業譲渡の影響が小さく会社の基礎的変更とまではいえないため株主総会での決議を省略しても問題ないという趣旨です。もっとも、一定期間内に株主総会での決議を否決しうるだけの反対株主が出現した場合は、株主総会を開催する必要があります(会社法468条3項)。さらに、事業の「重要な一部の譲渡」の場合に限りますが、譲渡する資産の帳簿価格が譲渡会社の純資産額の5分の1を超えないときは、株主総会の決議も不要であり、反対株主の株式買取請求権も発生しません(会社法467条1項2号かっこ書き。)
反対株主の株式買取請求
事業譲渡は、略式譲渡や簡易の事業譲受けといった例外的なケースを除き、基本的には会社そのものに本質的かつ重大な変更を生じさせる行為です。事業譲渡それ自体は株主の多数決(株主総会の特別決議による承認)で行えますが、当事会社の従前の株主の中には、事業譲渡に反対している少数派の株主もいるかもしれません。
そこで、事業譲渡においても、他の組織再編と同じく、事業譲渡に反対する株主に対しては、保有している株式を公正な価格で会社に買い取ってもらい会社から退出する機会を確保・保障するために、株式買取請求権が認められています(会社法469条、470条。組織再編における株式買取請求権の趣旨につき、最高裁決定平成23年4月19日)。
もっとも、例外的に、事業の全部を譲渡する事業譲渡において、当該事業譲渡を承認する株主総会の特別決議と同時に会社の解散を決議した場合(会社法471条3号)は、譲渡会社の反対株主には株式買取請求権がありません(会社法469条1項1号)。なぜなら、当事会社である譲渡会社が解散すれば、その後の清算手続において残余財産の分配により投下資本の回収を図れるからです。また、簡易の事業譲受けの場合も、譲受会社の基礎に大きな変更を生じさせるほどの規模ではないことから譲受会社の株主の利害に与える影響も小さいと考えられるため、反対株主に株式買取請求権は認められません(会社法469条1項2号)。
個々の資産・負債の名義変更・対抗要件具備
上記のとおり、事業譲渡は個々の権利・義務を一括して譲渡する行為ですから、民法の一般原則どおり、譲受人が義務(債務)を免責的に引き受ける場合は債権者の承諾が必要になりますし(民法472条3項)、権利の譲渡にあたっては権利の種類ごとに対抗要件を備える必要があります(ex民法177条、178条、467条)。
例えば、不動産であれば所有権移転登記(民法177条)、動産(自動車を除く)であれば引渡し(民法178条、182条1項、182条2項、183条、184条)(占有改定(民法183条)であっても「引渡し」にあたり対抗要件が認められることにつき最高裁昭和30年6月2日判決、指図による占有移転(民法184条)であっても「引渡し」にあたり対抗要件が認められることにつき最高裁昭和34年8月28日判決)、従業員との雇用契約であれば従業員との個別同意、債権譲渡であれば確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾(民法467条1項、2項)(※法人が債権を譲渡した場合は債権譲渡登記ファイルへの譲渡の登記により確定日付のある通知とすることが可能(債権の譲渡の対抗要件の特例等第4条1項))、普通自動車であれば登録(※軽自動車には登録制度が存在しないので、一般的な動産と同じく「引渡し」により対抗要件を具備します)です。
対抗要件を備えていないと、後から登場した第三者に自身の権利を奪われかねませんから、必ず対抗要件具備の手続きを行いましょう。
許認可の取得
事業譲渡の対象が許認可を要する事業の場合、許認可は当然には引き継がれませんから、譲受会社において許認可を取得しなければなりません。
以上が主な手続きですが、会社の規模感によってはさらに別途の手続きが必要になる場合があります。
まず、独占禁止法16条2項に定める基準を満たす当時会社が行う事業譲渡については、事前に公正取引委員会に対する届出が必要になります。概要、国内売上高合計額が200億円を超える会社(譲受会社)が、①国内売上高が30億円を超える会社の事業の全部の譲受けをしようとする場合、②他の会社の事業の重要部分の譲受けをしようとする場合であって、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が30億円を超える場合、③他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受けをしようとする場合であって,当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が30億円を超える場合には届出が必要となります。ただし、事業譲渡をしようとする当時会社同士が同一の企業結合集団に属する場合には届出が不要となります。「企業結合集団」とは,会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の最終親会社及び当該最終親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除きます。)から成る集団をいいます。
上場会社が会社分割を行う場合は、有価証券上場規程に従い適時開示を行う必要があります。開示内容は、各証券取引所が発行するガイドブックに記載されています。ガイドブックや過去の開示例を参照しながら、適時開示の準備を進めていくことになります。例えば、日本取引所グループ(JPX)の開示基準によれば、概要、事業譲渡により連結純資産が30%以上増減する場合や事業譲渡により直近の決算書と比較して連結売上高が10%以上増減する場合等は、開示が求められます。
このように、事業譲渡の当事会社の規模が大きかったり上場会社であったりする場合は、会社法上の手続に加えて公正取引員会への届出や証券取引所での情報開示といった別途の手続を行わなければなりません。
事業譲渡における注意点
事業譲渡に限らず、М&Aのどのスキーム(合併、事業譲渡等)においても特に重要な事項は、М&Aの対価に関する事項です。対価の額や内容が適切でないと、いずれかの当事会社で株主総会の承認決議が経られなかったり、多くの反対株主から株式買取請求権を行使されてしまいスケジュールどおりに事業譲渡を円滑に進められなくなったりする可能性があります。また、判例は、組織再編の対価が不公正であることそれ自体は組織再編の無効原因とならないとしていますが(東京高裁平成2年1月31日判決・最高裁判決平成5年10月5日(上告棄却))、株主総会の決議の際に当事会社の取締役等が株主に対して対価が公正であるかのように偽った場合は、決議が違法又は著しく不公正として承認決議の取消事由になるおそれはあります(会社法831条1項1号)。なお、学説の中には、略式事業譲渡等の場合には株主総会の特別決議による承認が不要であること、解散を決議し清算中の会社の事業譲渡においては反対株主の株式買取請求権が認められていないことから、株主保護を厚くするため、株主による差止請求(会社法360条)も可能であるとの見解もあります(弥永真生『演習会社法〈第2版〉』有斐閣(2010年)170頁)。
いずれにせよ、事業譲渡にあたっては、公正な譲渡価格の設定が求められます。
税金
事業譲渡では資産・負債が譲渡されるため、譲渡会社及び譲受会社の双方に対し、各種税金が課税されます。特に大規模な事業譲渡では、税金が非常に高額になるケースもありますから、事前に入念な試算やプランニングが必要になります。一般的には、のれんを償却し損金計上できる譲受会社(買い手)よりも、譲渡会社(売り手)の方が負担する税金が高額になりやすいです。
まず、譲渡会社に対して課される税金をご紹介します。譲渡会社は事業譲渡により譲渡対価(売却益)を得ますから、この利益に対して法人税が課されます。法人税については、当該事業譲渡の対象となっている事業以外の事業における税引前当期損失が出ていたり、青色繰越欠損金があったりする場合はこれと売却益とを相殺できるため、赤字が出ている状態で事業譲渡を行うと法人税を節税できる可能性が高いです。また、譲渡する資産が消費税の課税取引に該当する場合は消費税も発生します。この消費税は要注意で、実際の取引おいては、譲受会社から預かった消費税分の金額を納税するだけですので収支はプラスにもマイナスにもなりません。しかし、消費税を預かると、その時点でのキャッシュが増加しますから、資金に余裕ができたと勘違いしてしまうおそれがあります。特に、事業譲渡の規模が大きい場合は消費税も高額になりますから、見かけ上のキャッシュが大きく増加します。しかし、このキャッシュの中には納税する義務のある消費税が含まれていること意識しなければなりません。事業譲渡の事前・事後のタックスプランニングが重要といえるでしょう。
次に、譲受企業に課される税金をご紹介します。まず、譲渡会社と同じく、消費税が課税されます。資産の対価に加えて消費税分の金額を譲渡会社に支払い、納税は譲渡会社が行うことになります。そして、譲渡を受ける資産の中に土地や建物とった不動産がある場合、当該不動産につき不動産取得税が課税されます。不動産取得税の税率は固定資産税評価額の4%です。不動産については、加えて、対抗要件である所有権移転登記を具備するにあたり、登録免許税も課税されます。
事業譲渡に限ったはなしではありませんが、М&Aを行うにあたって税金の問題は避けては通れず、入念なタックスプランニングが求められます。タックスプランニングの結果、事業譲渡ではなく会社分割など他のスキームでМ&Aを進めることになったり、М&Aを進めること自体を中断せざるを得なかったりするケースも珍しくありません。
経営者の保証責任
多くの会社は、銀行等の金融機関から融資を受けています。そして、会社が融資を受けるに当たり、代表者個人が会社の返済債務を個人保証(連帯保証or第三者保証)しているケースがほとんどです。事業譲渡に際してこの代表者個人の保証責任の取り扱いがネックになることがあります。譲渡会社の代表者からすると、譲渡後も保証責任が存続すると譲渡した事業といつまでも関係が続くことになり、事業譲渡の本懐を遂げられない可能性があります。また、譲受会社から見ても、代表者の保証責任まで譲渡されてしまうと契約関係が複雑になりトラブルに巻き込まれるリスクを抱えます。そのため、可能な限り、代表者の保証責任は解除しておくことが望ましいです。
保証責任を解除する最も確実な方法は、返済債務を履行してしまうことです。担保を売却して返済に充てることでもよいですし、譲受会社が事業譲渡と同時に金融機関に返済してしまうことでもよいでしょう。また、譲受会社の代表者に保証責任を引き継いでもらうという方法もあります。この方法をとる場合には銀行との協議・同意が必要不可欠です(民法472条、472条の4参照)。
経営者の保証責任を検討するうえで役立つのが、「経営者保証に関するガイドライン」です。このガイドラインは、経営者による個人保証が経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという点に着目し、このような課題の解決を目的として策定されたものです。ガイドラインによれば、概要、①資産の所有や金銭のやり取りに関して、法人(会社)と経営者個人とが明確に区分・分離されている、②財務基盤が強化されており、法人(会社)のみの資産や収益力で返済が可能である、③金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されているの3つの要件を満たせば、経営者の個人保証を行うことなく融資を受けられたり、既に行っている経営者の個人保証を解除又は軽減することができたりする可能性があります。さらに、令和元年12月には、事業承継を円滑に進めるために「『経営者保証に関するガイドライン』の特則」が策定されました。ガイドラインの特則の内容は、概要、①事業承継時、新旧経営者からの個人保証(二重徴求)を原則として禁止する(※例外的に二重徴求が許されるケースを4種の取引に限定)、②後継者(譲受会社)となる経営者の個人保証は、事業承継の阻害要因となることを考慮して金融機関は慎重に判断する(個人保証を求めることで事業譲渡が頓挫するリスク、これによる地域経済の発展の阻害や金融機関自身への経営基盤への影響を考慮し、個人保証が必須か否かを真摯かつ柔軟に検討する)、③前経営者(譲渡会社)の個人保証も、令和2年4月1日からの民法改正で第三者保証の利用が制限されることや経営者以外の第三者保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立が求められていることを踏まえ保証契約の見直しを検討し、なおも個人保証を求めるのであれば前経営者の株式保有状況や会社の借入返済能力等を勘案して保証の必要性を慎重に検討するというものです。
ガイドラインやガイドラインの特則を活用することで、事業承継のネックになっている経営者の個人保証の見直しが図れるでしょう。
なお、ガイドラインもガイドラインの特則も、いずれも法令のような強制力はなく、あくまで自主的ルールに過ぎません。経営者の個人保証を解除するか否かは、最終的には融資をしている銀行等の金融機関の判断に委ねられることとなります。とはいえ、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と謳われており、関係各者の自発的な尊重・遵守が求められていますから、ガイドラインとガイドラインの特則を活用しない手はありません。
銀行の承諾の要否
ここまで見てきたとおり、経営者の個人保証は事業譲渡を進めるにあたり大きな障壁となります。そのため、事業譲渡の当時会社としては、個人保証を外すべく動くことになりますが、弁済以外の方法で外す場合は、銀行の承諾が必要です。個人保証も(連帯)保証契約であすから、それを解約するためには契約当事者である銀行の合意が必要となるからです。そして、銀行との交渉を有利に進めるためにも、前述した「経営者保証に関するガイドライン」「『経営者保証に関するガイドライン』の特則」が大いに活躍するのです。
譲渡会社の経営者の個人保証を譲受会社の代表者へ免責的に引き継がせる場合でも、債権者である銀行の承諾が求められますから(民法472条2項、3項)、いずれにせよ銀行との交渉は避けられないでしょう。
会社分割との比較
事業譲渡は、会社分割と比較されることが多いです。事業譲渡=会社の事業の全部又は一部の譲渡と、会社分割=会社の事業に関する権利義務の全部又は一部を移転することは、類似しているからです。法律上の手続きについてみても、両者は原則として株主総会の特別決議に承認が必要であることや反対株主の買取請求権が認められる点で共通します。
では、どこに違いがあるのかというと、主に3点あります。
まず1つめとして、効果とそれに伴う手続きの違いがあります。事業譲渡において譲受会社が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには債権者の承諾が必要(民法472条2項、3項)ですが、他方で、会社分割においては、債権者の承諾は不要であり吸収分割契約または新設分割計画に基づき契約上の地位が移転します(会社法759条1項、764条1項)。効果の面では会社分割の方がシンプルですが、会社分割を行うにあたっては、事業譲渡では要求されない債権者異議手続が必要となります(会社法789条1項2号、810条1項2号等)。これは、事業譲渡は個々の資産・負債を譲渡するものであるのに対し、会社分割は事業の権利義務の全部または一部をまとめて承継させるものであるという違いに由来します。
2つめとして、無効主張の方法の違いあります。事業譲渡の無効は、いつでも誰でも主張できるのに対し、会社分割の無効は、無効の訴えをもってのみ可能であり、無効の訴えを提起できる者も株主や取締役等に限られます(会社法828条1項、2項)。
さらに3つめとして、当事者となれる者の属性があります。事業譲渡の相手方は会社である必要はなく個人でも当事者となれますが、会社分割の相手方(承継を受ける側)は会社である必要があります(会社法2条29号、30号参照)。
М&Aのスキームとして事業譲渡と会社分割が候補となった場合は、上記の違いを意識し、ケースバイケースでその時点での具体的かつ個別的な事情を勘案してよりメリットの大きいスキームを選択することになるでしょう。
事業譲渡の活用方法
事業譲渡の大きな特徴は、譲渡対象となる個々の資産・負債ひとつひとつにつき譲渡手続きや対抗要件の具備が必要となる点にあります。これは、譲渡手続きが煩雑であるという点ではデメリットですが、譲渡対象を細かく限定できる点や限定をかけることで(法律上は)簿外債務の承継リスクを抑えられる点はメリットといえます。また、従業員との雇用契約も、譲渡にあたり当事者の事情に応じて再度設定できます。人員の整理・拡充のためには事業譲渡は効果的なスキームとなりえます。
買い手である譲受会社に特有のメリットとしては、事業譲渡を受けることで事業拡大や人員・技術の獲得が実現できます。また、譲渡を受けた“のれん”を償却し、損金として計上することにより、節税効果を望めるでしょう。
売り手である譲渡会社に特有のメリットとしては、不採算事業部門を譲渡することにより自社で存続させるメイン事業への経営資源集中・組織のスリム化を図ることができます。譲渡対価により経営再建を実現できる可能性もあります。
上記のとおり不採算部門の譲渡により経営再建を図る方法としても事業譲渡は有効ですが、詐害的会社分割に対する規制と同様、債権者を害するような詐害的事業譲渡に対しては規律が設けられています。具体的には、譲受会社に承継されない債務の債権者を害すること知って事業を譲渡(=詐害的事業譲渡)した場合には、残存債権者は、譲受会社に対し、承継した財産の価額を限度として当該債務の履行を請求できます(会社法23条の2第1項)。経営再建目的で事業譲渡を行う場合には特に注意が必要です。
法律上・税務上・会計上のデューデリジェンスやビジネスからの観点で検討し、М&Aのスキームとして事業譲渡が適切なのかあるいは他のスキームが適切なのか判断しましょう。
企業法務の最新情報をお届けする無料メールマガジン