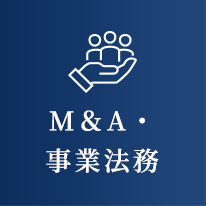M&Aによる事業売却に成功した事例
M&Aにおける株式価格の評価(IT企業及び通信販売会社の事例)
IT企業や通信販売会社は、特別の参入障壁がないために競争が激しく、特殊な商品や技術、販売網を有していない限り一定の売上を確保することは困難な業種であると考えられます。しかしそのような環境の中でも売り上げを伸ばして利益をあげ、M&Aによる事業売却の中で多額のキャピタルゲインを得ている社長もいらっしゃいます。次の事例は仮想の事例ですが、市場の環境変化の激しい業界においてはM&Aによって成功を治める可能性が高いことが分かります。
M&Aの背景事情
Aさんは、12年前にそれまで勤務していた医療機器販売の会社を辞め、30歳で独立を果たしました。最初は雑誌の広告欄に記載のあったある健康食品会社の販売代理店となり、インターネットを通じて健康食品の販売を行ってきました。自宅の近所のマンションの一室を6万円で借り、アルバイト社員数名を雇ってホームページで広告を行い、注文のあった人に商品を納品して代金を振り込んでもらうという仕組みです。健康食品は粗利が7割程度と利益率は大きいものの、顧客に認知されないとなかなか売上につながらないという難点があります。最初の数年間は年間の売上高が300万円から600万円とほとんど変わらず、仕入れ原価を差し引いた年間の粗利は100万円から300万円程度に限られていました。ここから事務所の家賃とパートへの人件費を差し引くと毎年赤字となり、親からの借入によって最低限の生活費で食いつなぐという生活を送っていました。
そのうち、知人からの勧めで化粧品を販売するようになりましたが、ある時扱っている化粧品が女性雑誌で取り上げられたことから急激に売り上げを伸ばすことができました。Aさんは特定のターゲットを対象とした雑誌の広告が強力な商品の吸引力を有することを知り、自分が特に気に入った商品に限定して女性誌への雑誌広告を行い、通信販売の方法で化粧品を販売するビジネスへの転換を図りました。その後、商品が売れるにしたがって広告方法も雑誌からテレビショッピングやインターネット広告へと移行し、プロパーの正社員を5名採用するとともに、アルバイト社員も20名に増員し、現在では年間売上12億円を達成することができました。
Aさんの会社の売上及び営業利益は次の通りです。
売上高 営業利益
平成15年 300万円 ▲150万円
平成16年 350万円 ▲100万円
平成17年 600万円 ▲200万円
平成18年 550万円 ▲200万円
平成19年 1200万円 100万円
平成20年 3500万円 200万円
平成21年 8000万円 1500万円
平成22年 3億5000万円 8000万円
平成23年 8億8000万円 2億6000万円
平成24年 12億円 3億3000万円
Aさんの会社の強みは何と言ってもしっかりとした売上を作っていることにあります。また、商品の特性から粗利率が非常に高く、アルバイトを活用することで経費を抑えることが出来る点も収益力の観点からは魅力的となります。Aさんはもともと雑誌や通販販売に関心がありましたので、自ら広告の企画を行い、広告会社と打ち合わせを行うなど、仕事のほとんどの時間を広告宣伝活動に当てています。
Aさんの会社の直近の損益計算書は次のようになっています。
売上高 12億円
売上原価 4億5000万円
販売管理費 4億3000万円
営業利益 3億2000万円
営業外収益 2000万円
営業外費用 1000万円
経常利益 3億3000万円
税引き後利益 2億円
株式の評価
Aさんの会社の特色は、売上高に対して売上原価が低いこと、営業利益が著しく大きいこと、長期の社歴はないが、年々売上高を増加させていることなどにあります。このようなAさんの会社に対して通信販売大手のB社から買収の申入れがありました。問題はAさんの会社のように近年著しく利益をあげている会社に対する評価をどのように行うかということにあります。株式の評価については様々な方法がありますので、どの方法を採用するのがこの事例において最も適切かを検討する必要があります。
時価純資産価額法
中小企業のM&Aにおいて最も多く用いられる評価方法です。M&Aの目的に沿うよう対象会社の貸借対照表に一定の修正を施し、修正貸借対照表から対象会社の純資産価額を算出します。その金額に営業権を加えたものが買収価格となります。会社に蓄積された資産をもとに評価を行いますので、コストアプローチとも言われます。但し、本件では、会社に蓄積された純資産はそれほど大きくなく、むしろ近年における売上高の増加をどのように評価するかという点に重点が置かれる必要があります。
類似会社比準法
上場類似会社の時価総額をもとに対象会社の価額を評価する方法です。類似の上場会社がある場合には、その上場会社の時価総額をEBITDAや税引後利益などの採用する指標で割り、対象会社のEBITDAや税引き後利益にその倍率をかけて株式価格を算出する方法です。例えば類似の上場会社の時価総額が30億円で、EBITDAが2億5000万円の場合、倍率は12倍になります。対象会社のEBITDAが1億2500万円であれば、対象会社の株式価値は15億円ということになります。類似会社比準法はマーケットアプローチとも言われます。但し、本件では、Aさんの会社の規模が上場会社ほど大きくないことから対象となる類似会社の抽出が必ずしも可能であるとは限りません。
収益還元法
税引き後営業利益を資本還元率で割り、調整を加えた上で株価を算出する方法です。企業の有する収益力に着目した計算方法であることから、インカムアプローチとも言われます。本件では、売上高及び利益が著しく増加していることに着目してM&Aが行われるものと思われますので、収益力に着目した収益還元法が最もふさわしいと考えられます。
収益還元法では、税引き後営業利益を資本還元率で除し、一定の調整を加えることで株価を算出することになります。資本還元率については、対象会社のリスクなどを加味した投資利回りと考えられます。本件の会社の場合、利益が毎年増加しているものの一定しているわけではなく変動の余地が大きいことや、ネット通販の経営環境、市場環境などを加味して検討される必要があります。市場金利が極めて低い状況であったとしても投資家からすれば比較的リスクの高い投資になりますので、10%から15%程度の還元率を要求されるのではないかと思います。もちろん資本還元率を何パーセントにするかについて一定の定めがあるわけではありません。結局は売主と買主の交渉により定まるということになります。
そこで、仮に資本還元率を10%として、収益還元法による株式価格を算出すると次のようになります(仮に預貯金3億円、借入金5億円とする)。
損益計算書の経常利益 3億3000万円
実行税率 40%
経常利益に対する法人税 1億3000万円
税引き後経常利益 2億円
資本還元率 10%
還元価格 2億円÷0.10%=20億円
預貯金・貸付金加算 3億円
借入金減額 5億円
調整後価格 20億円+3億円-5億円=18億円
従って、Aさんの会社の株式価格は18億円ということになります。Aさんとしては今後もっと売り上げをあげて会社を大きくしたいという要望がある一方、もともと小さな会社で苦労を多くしてきた経緯がありますので、一旦会社の売却により売却資金を確保し、その上で今後の生活を見つめていきたいという考えもあります。Aさんは色々と悩まれた後、最終的にB社からの買収申入れを受け入れることになりました。
株式譲渡益への課税
なお、Aさんの株式売却価格は18億円ですので、そこから株式の取得原価(例えば1000万円)を控除した残額(例えば17億9000万円)が株式譲渡益になりますので、Aさんに対しては17億9000万円に対する20%(3億5800万円)の申告分離課税によるキャピタルゲイン課税が課せられることになります。結局Aさんの手取り額は17億9000万円+1000万円-3億5800万円=14億4200万円となります。
コンサルタント契約の締結
本件のように会社の代表者が急激に会社を大きくした場合は、会社の売り上げや販売戦略などについても代表者の力量に負うところが極めて大きく、買収を行った会社から引き続き代表者として(あるいは顧問として)会社の経営に関与してほしいと要望されることが多くあります。このような場合、Aさんとしては、どのような条件で買収会社に雇われるのか(例えば従前の会社の顧問として、買収完了後最低6か月間は、毎週最低3日間会社に勤務し、販売政策やマーケティング活動に協力すること、会社はAさんの労務の対価として毎月200万円の支払を行うことなど)を明確にした雇用契約書やコンサルタント契約書などを作成しておく必要があります。
上記は通信販売会社に関する事例をもとに著しく収益を伸ばした会社のM&Aについて説明するものですが、買収を行う会社においても自己の売上を瞬時に上げることが出来たり、際立った販売政策や販売戦略を有する人を内部に取り込み、自社製品の売上増加につなげていくことが出来るなど大きなメリットがあります。そこで、インターネットやテレビ通販を利用した通信販売だけでなく、IT系の会社や、レストランのチェーン店などにおいても同様のM&Aがなされることは多くあります。
当事務所で取り扱った事例においても、事業承継や再生型のM&Aとは異なり、一代で会社を大きくした若手の経営者が、会社を売却し、会社の売却資金により次の投資対象を検討したり、上場企業の傘下に入ることでより大きな販売ないし研究開発ができることを目的として積極的な観点からM&Aを活用する事例もだんだん多くなっています。アメリカにおいては、会社の売却によって多額の売却資金を得て、早期にリタイヤしたり、次の投資により資産をより大きくしていこうと考える人が増えていますが、日本においても今後このような事例は一層増えて来るのではないかと考えています。