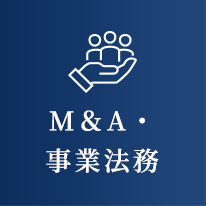デューデリジェンスにおける労務問題のチェックポイント
労務関係の資料
労務問題を確認するためには、従業員名簿、組織図、就業規則、雇用契約書、退職金規定、競業避止及び秘密保持に関する契約、職務発明に関する覚書、従業員持株規約など様々な資料を確認する必要があります。また、労働基準監督署へ届けられた三六協定書、労使協議により作成された労働協約、労働組合に関する資料なども対象となります。
従業員、組織図
中小企業のM&Aの場合、従業員一人一人のウエイトが重要になりますので、従業員名簿により従業員の年齢、勤続年数、男女の別、役職などを確認し、それぞれの履歴書、専門資格の有無、給与の額なども検討する必要があります。平均勤続年数が短い会社や社員の平均年齢が極めて若い会社については、社員が転職しやすいということになりますし、反対に社員の平均勤続年数が極めて長く、平均年齢が40歳を超えるような会社の場合には、会社の雰囲気がよく、長年継続して勤務したくなる会社であるとの推測が成り立つ一方、会社の中で新陳代謝が行われておらず、マンネリ化しているリスクがある可能性もあります。
キーマンへのインタビュー
また、特別の専門的能力や、技術開発力、組織をまとめる力、営業能力等を有するいわゆるキーマンという人がいる場合には、キーマンに個別にインタビューを行い、会社への帰属意識や、今後も継続して会社の職務を行う意思があるかどうかを確認するなどの作業が必要になります。ある中小企業のM&Aでは、対象会社の営業部長がほとんど一人で会社の全ての売り上げを出していることがありました。
また、大会社の一部を会社分割により取得したケースにおいて、40名の承継する社員のうち、10名程度をキーマンとして抽出し、そのキーマンが会社分割後1年以内に会社を辞めた場合には、1人につき3000万円を買収金額から減額するという契約を行ったことがあります。そのケースでは、1年以内にかなりの数のキーマンがやめることになり、買収側と買収される側との間で金額の調整をどのようにするかでもめたケースがありました。いわゆるキーマンが会社の中にしっかり根付いており、企業買収の後にも継続して会社に対する忠誠心を持ってもらえるかどうかは、会社の買収において極めて重要な要素になります。
就業規則、雇用契約書
就業規則や雇用契約書の確認も重要です。期間の定めなく採用される正社員の場合、雇用契約書の作成が義務付けられておらず、雇用契約書のない場合の方が通常です。但し、期間の定めのない労働者に対しても、労働条件明示義務はありますので、会社は採用時において勤務時間、勤務場所、基本給、休暇等の基本的な労働条件について労働条件通知書などにとりまとめ、新入社員に対して示すことが要求されます。一方、アルバイトや有期の雇用契約については、労働基準法により雇用契約書の作成が義務付けられていますので、雇用契約書が作成されているのが通常です。法務監査の過程では、労働条件の明示がきちんとなされているかどうか、アルバイト社員などについては、雇用契約書が締結されているかどうかを確認することになります。
常時従業員が10人以上いる会社については、就業規則の作成が義務付けられていますし、従業員の数が10名以下であっても従業員の基本的な権利義務を定めるメリットが大きいことから、ほとんどの会社において就業規則があるのではないかと思われます。就業規則を作成していない場合、問題を起こした従業員を解雇しようとしても、就業規則上の要件がはっきりしないことから、解雇が困難になるという事態も生じえます。また、従業員の側でも、いつでも勝手に雇用条件を変更されるのではないかと心配せざるを得ないことになりますので、安心して業務に取り組めないということになってしまいます。
年次有給休暇
就業規則の内容を確認すると年次有給休暇に関する規定に不備がみられることが多くあります。法令上、6か月以上勤務した社員については、原則として、最低10日間の年次有給休暇を与えることが必要で、年次有給休暇の日数はその後12日、14日と年度ごとに増えていくことになります。
年次有給休暇を消化しなかった場合、未消化の有給休暇日数について翌年度に繰り越されるかどうかは会社の規定で定めることが出来ることになっています。多くの会社では1年間のみ翌年度に繰り越しをすることが出来るとされています。例えば平成26年度の有給休暇日数が10日間、27年度が12日間、28年度が14日間として、26年度に5日しか有給休暇を使用しなければ、平成27年度には繰り越された5日と本来の12日を合わせた17日の休暇を取ることが出来ることになります。一方、27年度に10日間休みを取ったとすれば、26年度の5日間と、27年度の5日間を消化したことになりますので、28年度に繰り越される年次有給休暇は7日間となり、平成28年度は本来の14日間と7日間を足した21日の有給休暇を取得しえることになります。
近年までは、忙しすぎて年次有給休暇を取得したくても取得できないとか、会社の雰囲気で、年次有給休暇を取得できないということが多くありましたが、近年では労働者の権利という認識が広まっているため、労働者の側から年次有給休暇の取得申請が積極的になされています。年次有給休暇の取得を制限することは実質上難しいと考えられます。
一方、近年では、国民の祝日が多く規定されましたので、土曜日日曜日以外の国民の祝日による休暇の日数も極めて多くなっています。実質的な勤務日数は月20日程度と思われます。この点からすると20日以上の年次有給休暇を取得する場合、毎年ほとんど1月全部を休暇として休むことになりますので、経営者の視点からすれば休暇が多すぎるということになるかと思われます。年次有給休暇を繰り延べするかどうかは、法律の規定や国民の祝日の日数、年末年始の臨時休暇等の状況も十分に勘案して慎重に判断しなければならない問題と思われます。
なお、年次有給休暇の繰越は認めないが、未消化の有給休暇を買い取る制度を採用している会社も多くあります。現在の状況を考えれば、こちらの制度の方が現実に即しているかもしれません。
外資系企業の雇用契約書
外資系企業においては、雇用契約書を作成するのがほとんど当然と考えられており、雇用条件や解雇の条件などが細かく規定されているのが通常です。退職金の支給の有無やストックオプション、社会保障関係の費用負担なども詳細に定められています。外資系企業の場合、労働紛争が生じた場合には、まず雇用契約書の内容を確認し、それによりどのような権利義務関係が生じているのかを確認することになります。例えば正当な解雇事由に該当するかどうか、解雇が正当な場合に退職金が支給されるのかどうか、ストックオプションはどうなるかなどを確認する必要があります。但し、労働法は強行法規と言われ、仮に本拠地が海外にある会社であったとしても、当該従業員が日本国内で働いていた場合には、日本法が適用になります。国際私法上労働者の法律関係は、法人の本拠地ではなく、就労地の法律が適用になるとされているからです。また、裁判管轄についても、日本で業務している社員については、日本の裁判管轄が認められ、仮に雇用契約書の中で、外国の裁判所を専属裁判管轄と定めている場合であっても、当該規程の適用は排除され、日本の裁判管轄が適用になります。
従って、外資系企業の労務関係については、雇用契約書の内容が第一に重要となりますが、日本の労働法が強制的に適用になりますので、日本の労働法についても確認を要することになります。例えば、日本の労働法上、従業員の解雇については、正当な事由が要求され、正当事由を欠く解雇は無効とされていますので、雇用契約書において解雇できる場合であっても、裁判上は解雇が認められない可能性もあります。整理解雇についても、最高裁判所が定めた整理解雇の4要件は依然として適用になることになります。また、雇用契約書において基本給の中に残業代が含まれていると規定されていたとしても、どの範囲までの労働時間について特別手当の中に含まれており、それを超える範囲の残業について残業手当を支給すべきかどうかについての判断は日本の裁判所が日本の法律に基づいて判断することになります。
残業と三六協定
変形労働時間制や営業職の例外などの場合を除き、法律上従業員の勤務時間は一日8時間とされるのが原則で(但しこれより短い労働時間を定めることは当然可能です)、会社としては、従業員に対して自由に残業を命じることができるわけではありません。会社が従業員に残業を命じるためには、従業員の代表者又は組合との間で、いわゆる三六協定と呼ばれる協定書を締結し、これを労働基準監督署に届出ておく必要があります。法務監査の中では三六協定書の作成があるかどうか、三六協定書の写しに労働基準監督署による受付印がなされているかどうかを確認します。
三六協定を結ぶ従業員代表は、従業員の過半数の賛成により選ばれた人ということになりますが、多くの中小企業においては、経営者の側から従業員を代表してくれそうな人を選びその人に協定書にサインをしてもらうという形をとるのが通常ではないかと思います。組合がある場合には、組合代表者と締結する必要がありますが、組合がない場合にわざわざ組合を作る必要はありません。三六協定書では、例えば月40時間など、一月に命じることができる最大限の残業時間数を定めておく必要があり、実際にも従業員の残業時間がその範囲内にとどまっている必要があります。
秘密保持義務、競業避止義務、職務発明の帰属に関する覚書
会社の顧客情報や製品の製造方法など会社には色々な重要な情報があり、これがライバル企業など他社に漏れた場合には会社にとって重大な損失が生じる可能性があります。また、会社を退職した従業員が会社の秘密情報を使って新規企業を立ち上げたりすることも会社にとっては許されない事と考えられます。そこで多くの会社においては、従業員との間で秘密保持契約書を締結し、会社の情報を外部に漏えいしない事や、会社の秘密情報を会社の事業目的以外で使用しないことを義務付けています。
一方、会社の社員が会社を退職した後にライバル企業に勤めたり、自ら会社を興して会社の業務と競業する事業を始めることについては、競業避止契約が締結されていないと抑止できないことになります。もちろん従業員の退職時に、当該従業員に対して競業避止義務の誓約書に調印するよう求めることもありますが、従業員から任意にサインしてもらえないこともあります。そこで、会社に就職する段階で競業避止義務に関する覚書についても同意書を取っておくのが好ましいと考えられます。私どもが扱った事例においても、いくつかの会社では、従業員が退職する際に、競業避止義務の誓約書に調印するよう求めたところ、従業員がこれを拒否したため、会社が退職金の支給をストップし、従業員から退職金の支払いを求める訴訟が提起されるという事例が多くあります。入社の段階で競業避止義務契約書を締結していればこのような紛争は防げたのではないかと思われます。
最近では従業員から職務発明の対価を求められるケースも多くあります。特許法の改正により適正な金額の対価を支払った場合には、会社が職務発明を譲り受けることが出来るとされましたので、就業規則などの改正により職務発明が会社に帰属すること、会社から発明を行った従業員への対価の支給に関する規定が定められるようになりました。
しかし、一方で、特許などについては、出願時に発明者の名前が記載されるようになっており、将来特許権の処分を行おうとする段階で発明者から同意が得られず困ってしまうことが良くみられます(会社分割など将来の組織再編などの過程で問題とされることがあります)。発明についても正当な対価の交付を行うなどして、できるだけ会社に権利が帰属するよう予め対策を講じておく必要があると思われます。なお、著作権については、職務上著作については会社に権利が帰属することが法律上定められています。
個人情報保護規定との関係
最近は、いろいろなコンサルタントの活動により詳細な個人情報保護規定を有している会社が多くなっています。このような会社の個人情報保護規定では、会社の社長を最高管理者として、個人情報の不適切な取り扱いをチェックするような体制がとられることになっています。また、個人情報保護委員会を設けて、個人情報の棚卸が適正になされているかどうかや不適切な個人情報の取り扱いがなされていないかどうかを判断するとされています。非常に詳細な規定が整備されていますが、実際に規定に沿った運用がなされているかどうかを確認することが重要です。
企業法務の最新情報をお届けする無料メールマガジン